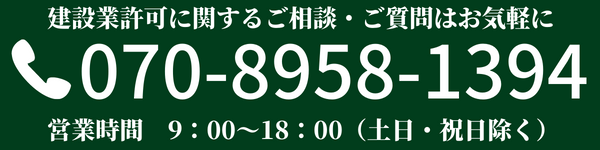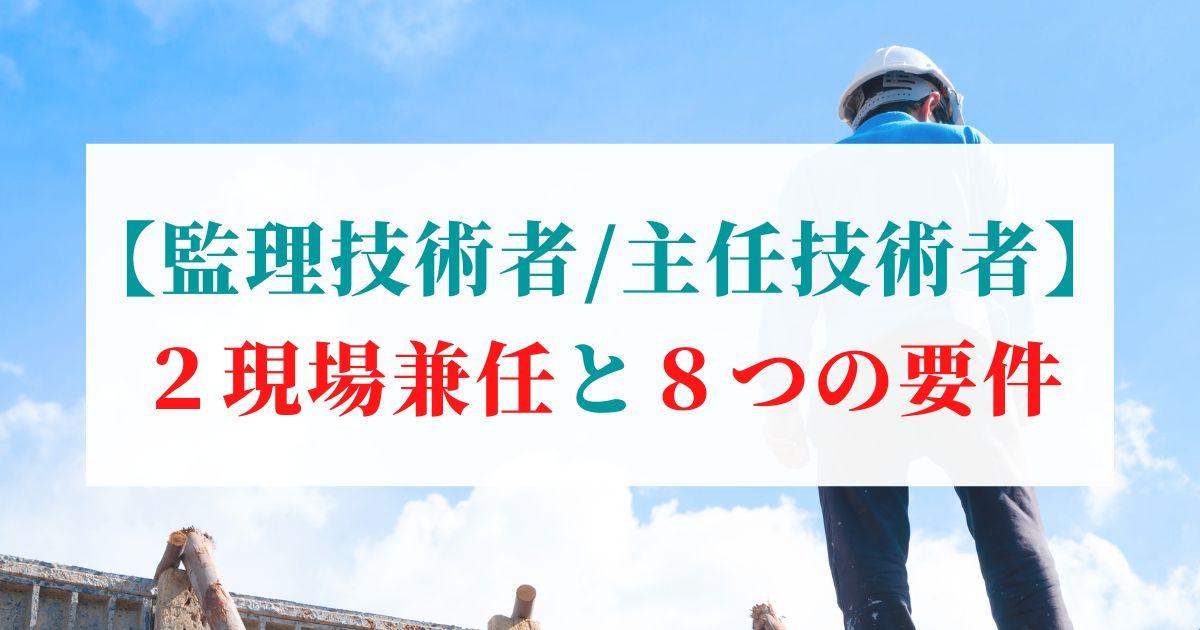
こんにちは。東京都八王子市にある行政書士MSオフィス代表の森本さやかです。当オフィスは建設業許可を専門としており、建設業に関するあらゆるお悩みを解決すべく、皆様のサポートをさせていただいております。
今回は「監理技術者・主任技術者の2現場兼任とその要件」について解説いたします。(監理技術者・主任技術者については以下の記事を参照してください。)
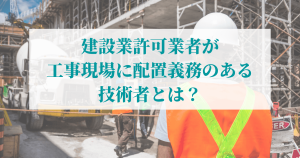
建設工事に置くことが求められている監理技術者又は主任技術者は、請負金額が一定金額以上の場合には、工事現場毎に「専任」で置くこととされています。(一定金額については以下の記事を参照してください。)
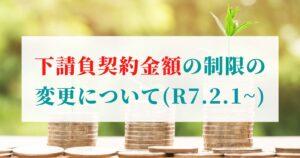
今般、生産性向上に寄与するため、情報通信機器を活用する等の8つの要件(後述)を満たした場合に、監理技術者又は主任技術者が2現場を兼任をすることができる制度が新設されました。
本記事では、その8つの要件を中心に詳細に解説していきますので最後までお読みいただけますと幸いです。
2現場兼任の8つの要件(監理技術者・主任技術者)
監理技術者・主任技術者が2現場兼任するための8つの要件は以下のとおりです。
- 請負金額が1億円未満(建築一式工事の場合は2億円未満)
- 兼任現場数が2工事現場以下
- 工事現場間の距離が1日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内
- 下請次数が3次まで
- 連絡員の配置
- 施工体制を確認する情報通信技術の措置
- 人員の配置を示す計画書の作成、保存等
- 現場状況の確認のための情報通信機器の設置
それでは①~⑧についてそれぞれ詳しく見ていきましょう。
① 請負金額が1億円未満(建築一式工事の場合は2億円未満)
兼任する各建設工事が、1億円未満(建築一式の場合は2億円未満)である必要があります。
なお、工事途中において、請負代金の額が1億円(建築一式工事の場合は2億円)以上となった場合には、それ以降は専任特例を活用できず、主任技術者又は監理技術者を専任で配置しなければなりません。
② 兼任現場数が2工事現場以下
監理技術者・主任技術者は、2現場を超えて兼任することはできません。最大で2現場までです。
また、「専任特例1号を活用した工事現場」と「専任を要しない工事現場」を同一の主任技術者又は監理技術者が兼務することは可能です。
ただし、「専任を要しない工事現場」についても、専任特例1号の全ての要件(請負金額除く)を満たし、かつ全ての工事現場の数が2を超えないようにする必要があります。
③ 工事現場間の距離が1日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内
移動時間は片道に要する時間になります。移動時間の判断については、当該工事に関し、通常の移動手段(自動車など)の利用を前提に確実に実施できる手段により行う必要があります。
④ 下請次数が3次まで
当該建設業者が注文者となった下請契約から数えて、下請次数が3を超えないようにする必要があります。
なお、工事途中において、下請次数が3を超えた場合には、それ以降は専任特例は活用できず、主任技術者又は監理技術者を専任で配置しなければなりません。
⑤ 連絡員の配置
連絡員とは?
連絡員とは、建設工事を請け負つた建設業者が主任技術者又は監理技術者との連絡その他必要な措置を講ずるための者(当該建設工事が土木一式工事又は建築一式工事である場合は、当該工事に関する実務の経験を1年以上有する者に限る。)のことです。
連絡員としての業務は、具体的には、例えば工程会議や品質検査等が2つの工事現場で同時期に行われる場合に、監理技術者等が遠隔から指示等するにあたって、工事現場側にて適切に伝達する等、円滑な施工管理の補助を行う(事故等対応含む)こと等です。
連絡員に必要な実務の経験として認められる内容は、営業所技術者(主任技術者)の実務の経験として認められる経験の考え方と同じです。
連絡員設置の注意事項
連絡員は、各工事に置く必要があります。なお、同一の連絡員が複数の建設工事の連絡員を兼務することは可能です。また1つの建設工事に複数の連絡員を配置することも可能です。
連絡員に当該建設工事への専任や常駐である必要はありません。連絡員の雇用形態については、直接的・恒常的雇用関係である必要もありません。ただし、連絡員は当該請負会社が配置するものであり、施工管理の最終的な責任は請負会社が負うことに留意が必要です。
⑥ 施工体制を確認する情報通信技術の措置
建設工事を請け負った建設業者が、当該工事現場の施工体制を主任技術者又は監理技術者が情報通信技術を利用する方法により確認するための措置を講じていることが必要です。
情報通信技術については、現場作業員の入退場が遠隔から確認できるものとし、CCUS又はCCUSとAPI連携したシステムであることが望ましいが、その他のシステムであっても、遠隔から現場作業員の入退場が確認できるシステムであれば可能とされています。
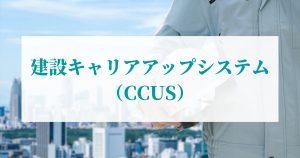
⑦ 人員の配置を示す計画書の作成、保存等
建設工事を請け負った建設業者が、次に掲げる事項を記載した人員の配置を示す「計画書」を作成し、当該工事現場に備え置く必要があります。
また、作成した計画書は、建設工事の目的物を引き渡したときから5年間(発注者と締結した住宅を新築する建設工事に係るものは10年間)、営業所で保存する必要があります。
- 当該建設業者の名称及び所在地
- 主任技術者又は監理技術者の氏名
- 当該主任技術者又は監理技術者の1日あたりの労働時間のうち労働基準法第32条第1項の労働時間を超えるものの見込み及び当該労働時間の実績
- 当該建設工事に係る次の事項
- 名称及び工事現場の所在地
- 建設工事の内容
- 当該建設工事の請負代金の額
- 第1号の移動時間
- 1次下請契約、2次下請契約及び3次下請契約のうち実際に締結されたもの
- 第17条の2第3号の者の氏名・所属会社及び当該建設工事に関する実務の経験の内容
(実務の経験の内容については、当該建設工事が土木一式工事又は建築一式工事である場合に記載) - 施工体制を確認する情報通信技術の措置
- 現場状況の確認のための情報通信機器の設置
⑧ 現場状況の確認のための情報通信機器の設置
主任技術者又は監理技術者が当該工事現場以外の場所から当該工事現場の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器が設置され、かつ、当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていることが必要です。
情報通信機器については、遠隔の現場との必要な情報のやりとりを確実に実施できるものであれば良く、一般的なスマートフォンやタブレット端末、WEB会議システムでも差し支えありません。
通信環境については、例えば、山間部等における工事現場において、遠隔からの確実な情報のやりとりができない場合はこの要件に該当しません。
まとめ
今回は「監理技術者・主任技術者の2現場兼任とその要件」解説いたしました。2現場兼任の8つの要件は以下のとおりです。
- 請負金額が1億円未満(建築一式工事の場合は2億円未満)
- 兼任現場数が2工事現場以下
- 工事現場間の距離が1日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内
- 下請次数が3次まで
- 連絡員の配置
- 施工体制を確認する情報通信技術の措置
- 人員の配置を示す計画書の作成、保存等
- 現場状況の確認のための情報通信機器の設置
以上です。ご参考になりましたでしょうか。
お困りのこと・相談したいことがございましたら下記のお問い合わせフォームからお願いいたします。